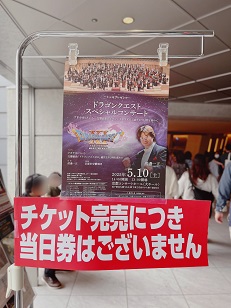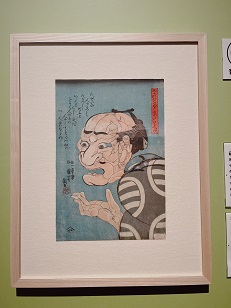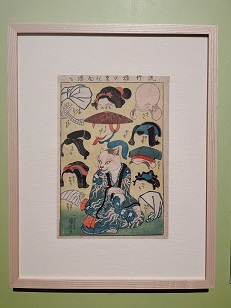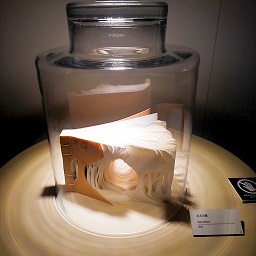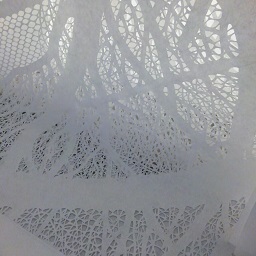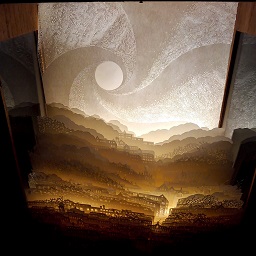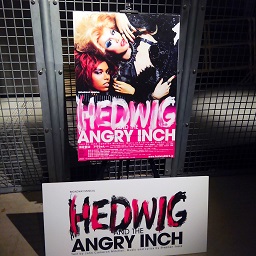泣いた……歌舞伎、野田版・桜の森の満開の下、良かったよ……。
これは劇場に行かなかった自分に、愛と涙の全力グーパンだよな。
すいません、相変わらずこの舞台に関しては、語りたくなります。
内容といい、時代背景といい、幽玄な雰囲気といい、衣装といい、
歌舞伎との相性が抜群であろうことは重々承知しておりましたが、
いやあ、遊眠社時代を彷彿とさせる、本当に素晴らしい舞台でした。
元祖をきちんと踏まえた上での進化は、流石は歌舞伎舞台。
この手の引継ぎを繰り返し続けていた、伝統芸能のお家芸ですね。
キャストに関しては、流石に伝統芸能を極めた歌舞伎役者陣、
私如きが口出しする方が野暮なレベルの、抜群な安心の安定感。
特に、勘九郎丈の耳男は、野田耳男のDNAを正当に引き継ぎつつ、
「らしさ」もしっかり出されたはまり役だったのではないでしょうか。
個人的には、野田耳男と並ぶレベルで好きかもしれません。
七之助丈の夜長姫は、正直、登場シーンでは「?」と思いましたが、
物語が進むにつれて違和感が薄れて、馴染んでいきました。
夜長姫は二つの声音を使いますが、特に鬼の声は非常に素晴らしく、
この低いのに「女性の声」と思わせる力量は、流石は女形役者さん。
ただ、「鈴が鳴るような無邪気な笑い声」は、ちょっと難しかったかな。
何処までも無垢で無邪気な永遠の女の子……とはやや趣が異なりますが、
それでも品があり、如何にも姫らしく、且つ醸し出される妖艶さがあり、
これはこれで、歌舞伎の夜長姫としての見応えがありました。
オオアマの幸四郎丈は、ある意味納得のキャスティングでしたね。
ザ・王子様だった天海さんとは異なり、腹黒さが垣間見える正統派権力者。
小綺麗な中にも小賢しさが漂い、朧の森然り、研辰の討たれ然り、
染五郎時代からこういう役どころがホント似合うなあ。<誉め言葉
太々しさ漂う猿弥マナコは、ある意味一番イメージに近い気がします。
古典芸能の役者だけあり、きちんとした土台のある動きは見事で、
所作も美しく、たおやかで、見せ場はきちんとクローズアップされ、
夜長姫の倒れるシーンや、立ち回りなどは「凄い……」と声が漏れました。
三名人がノミを振るうシーンと、特にラストのクライマックスシーンは、
元より古典芸能を意識していただけに、寧ろ彼らの土壇場でしょうね。
ビジュアルの美しさと考えると、ある意味こちらが上かもしれません。
この歌舞伎の「見せ方」の熟知された感は、もう流石としか言えないな。
尚、嬉しかったのが「私のお父さま」と「SUO GAN」の採用。
オペラと外国の子守歌が流れる異色の歌舞伎ですが、
この舞台において、この選曲は本当に神懸っていると思います。
野田舞台は、ある意味歌舞伎とは真逆に、過剰なまでの動きが特徴ですが、
それを歌舞伎舞台で見ることが出来たのは、非常に面白かったです。
案外この歌舞伎版が、一番万人受けが良く、判りやすいのかもしれません。
ぐっとシンプルになった「NODA MAP」での再演と違い、
この歌舞伎ならではの贅沢な豪華絢爛さも、残してほしい魅力があります。
人気のある舞台だし、歌舞伎演目としても申し分ない作品なので、
是非とも、是非とも!! 勘九郎耳男で再演して欲しい所存でございます。